
マインドフルネスとは
マインドフルネスのルーツは日本の座禅にあると言われています。
その座禅には、只管打坐を唱えた道元禅師の曹洞宗と、公案を唱えた栄西の臨済宗との二派があります。マインドフルネスは公案を用いる事はありませんので、宗教的な事を排除して、各々の心を整えていく事にスポットを当てた手法になります。
私たちの住む現代社会はストレス社会と言われています。その現代社会ではストレスから逃れる事はできません。複雑に変化を繰り返して行く社会構造の中で、わかりやすく言いますと、多くの人が常にイライラしている状態になります。
例えば、過去の様々な記憶が頭の中をぐるぐるとめぐったり、先々の不安が繰り返し襲って来るような心持ちになったりしてきます。すると、お仕事や家事育児等に取り組み難くなって来ることが起きて来ます。
その事によりマインドフルネスを取り入れる事により、ストレスから逃れる事を考えるのではなくストレスの中にいても、自分らしさを失わずに、自分らしく生きていく事が出来ます。
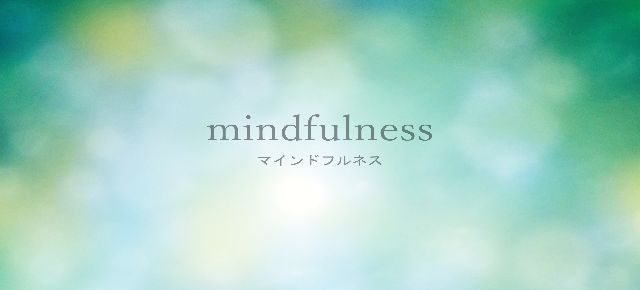
オリジナルマインドフルネス
オリジナル・マインドフルネス心理療法のご紹介
私がご提供するオリジナル・マインドフルネス心理療法は、単なる技法の提供ではありません。人生を通して深めてきた人間理解と、苦しみに寄り添う姿勢をもとに構築された、心に深く届く実践法です。
そして、自分の中に眠っている内なるパワーを引き出して行きます。
私自身、20代から社会貢献を志し、ボランティア活動に力を注いできました。その中で、うつ病に苦しむ知人がマインドフルネスの実践によって次第に回復していく姿に衝撃を受けたことが、今の活動の原点です。この出来事を契機に、私の人生の中心は「苦しむ人の心に寄り添うこと」へと移っていきました。
現在では、マインドフルネス瞑想療法士として、うつ病・不安障害・パニック障害・PTSDなど、現代社会に多い心の課題を抱える方々に対して、実践的なサポートを行っています。活動歴は15年を超え、延べ650名以上の方と出会い、無料相談を通してその心の声に耳を傾けてきました。病院に通っても改善が見られない方、薬の副作用に不安を感じている方にとって、心の回復に向けた“もう一つの道”として、この療法は支持されています。
このオリジナル・マインドフルネスは、私自身の生い立ち――母子家庭での幼少期、働きながらの学業、家族の介護に専念した14年、そして人生をかけた社会貢献――といったすべての経験から生まれたものです。理論だけではなく、「人の痛みに共に向き合ってきた実感」が、この療法の根幹にあります。
法人としては2010年に「マインドフルメイト」を設立し、2015年からは非営利型一般社団法人として正式に活動。現在は甲府・八王子・東京(八重洲・日比谷)・名古屋にて、個別支援・相談会・講座を展開しています。また、マインドフルネス乃学校の学校長として、未来の実践者育成にも力を注いでいます。
このオリジナル・マインドフルネスは、「心の深い苦しみと本気で向き合いたい」と願う方にこそ体験していただきたい療法です。単なるテクニックではなく、生きる力を再び取り戻す“道”として、あなたと共に歩んでいけることを願っています。
クリック ⇒

副交感神経が優位になる呼吸
人間は無意識に呼吸をしていますが、実はその呼吸は自立神経に作用しています。
息を吸う = 交感神経に作用する
息を吐く = 副交感神経に作用する
交感神経は活動的な時に活躍します。
ストレスが掛かっている時は、交感神経が活発に働いています。
ご自身が、ストレスを感じている時や、変な思考(考えや、マイナス思考等)が働く時には、
ご自身が、自覚する事はほとんどありませんが、交感神経が活発に働いています。
その結果、ストレスホルモンの過分泌が起こって来ます。
そうすると自律神経にも悪影響。
その結果、気が重くなったり、心臓がドキドキしたり、のどに石があるようにつまったり、
胃が痛くなったり、頭痛がしたり、吐き気がしたり・・・・ありとあらゆる体調の不調が出て来たりします。
副交感神経は、交感神経のあらゆる作用を鎮める働きがあるのです。
だから副交感神経が優位になるとリラックスして、それらの症状が落ち着いてきます。
その繰り返しの結果が自律神経を整えて来ます。

副交感神経を優位にする呼吸法
姿勢を正し、目を閉じずに呼吸法を行ってください。
斜め前をぼ~~と見る感じで行います。
音、目に見えるもの、空気感などをシャットアウトするのではなく
すべて受け入れて行います。(テレビや家族の話声もそのままに、運転しながらでもOK。)
始めは普通(無意識)の呼吸をします。
呼吸に意識を向けます。(この時、何も考えない・・・)吸って-・吐いて-・吸って-・吐いて-。
次に、ゆっくり呼吸をして、吸う方を短く、吐く方を吸う方の時間より2~3倍程度長くします。
この事を、20~30回ほど繰り返します。
(気を付ける事 ⇒ 苦しくなるほど吐かないこと)
これを長く続けると、副交感神経が優位になり、交感神経で興奮した神経が静まっていくという訳です。
ここで大事なのは、腹式呼吸や深い呼吸はしないことです。
この方法で、一日の生活の中でストレスを感じた時や、息苦しさを感じた時、疲れるなーと思った時に、
そのつど、一日に何度でも・何度でも、繰り返し行います。
その時に行う回数:20回~30回程度の呼吸法
この呼吸法をやっている内にも、ネガティブな考えがいっぱい浮かんでくるかもしれません。
実は、『思考に走らない』っていうのが大事なのだそうです。
よく座禅を組んでいる場面で、邪念を振り払いなさい。みたいな感じで
ビックなおしゃもじみたいなので、肩をたたかれるじゃないですか・・・
あのように、何も考えてはいけない。
でもそう言われてもどうしても何か考えていて考えに落ちていて、
考えに落ちているそのことさえ気が付かない事があります。
(考えている方が楽です。考えない時間をつくるのは大切ですが、チョット慣れるまで大変です)
そこで有効なのが【ゆっくり呼吸法(数える)】
この方がやりやすいかも、(20~30回ほど繰り返します。)
(声に出さず、頭の中で・・・)
先ほどの呼吸法の要領で・・・・
吐くとき ひと~~~ 吸う時 つ
次に吐くとき ふた~~ 吸う時 つ
1.呼吸するたびに、ひとつ
2.呼吸目は、ふたつ
3.呼吸目は、みっつ
と数えて とぉ(10)まで数えます。
10(とぉ)まで数えたら、また1(ひとつ)から数えます。
とぉまで行ったらまたひとつに戻る・・・
しかし・・・これが簡単なようで簡単じゃない
とぉまで行ってもなぜか次は じゅういち(11)とか
頭の中で言っちゃってますし・・・汗
しらずに30越えもあったりして・・・大汗
一度やってみてください。
こうやって10を超えてしまうということは、
必ず何かを考えていたということになります。
あ!10を超えてた・・・考えてた
と思ったらすぐまた 1から数えなおします。
自分は大丈夫、10まで数えたらちゃんと1へ戻れる
などと思っていても、結構数え進んでいるから
びっくりです。
思考に走ってどつぼにはまっている自分を確認することもできます。
早く考えている事に気づいてまた1から数える。
その思考が良いことであっても悪いことであっても止める。
ということが大事です。
生活の中に、いっぱい出来るだけ何度もこの呼吸法を取り入れます。

ポイントは続ける事です。
【参考】
行う時 ストレスが掛かっていると気付いた時。
例-お客様の対応でストレスが掛かった時
長時間の仕事の時
デスクでチョット時間が空いた時
トイレの中で、
車の運転をしながら、(安全運転に配慮して)
出来るだけ多く行うと効果的になります。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
【参考】
行う時 ストレスが掛かっていると気付いた時。
例-家事が思うように出来ない時
あれも、これもしようと考えてしまった時
ミスった、と気付いた時、
子育てが旨く行かない時
車の運転をしながら、(安全運転に配慮して)
出来るだけ多く行うと効果的になります。
マインドフルネスを熟知した指導者の基で行う。
マインドフルネスの効果を最大限に引き出すためには、熟練した指導者のもとで正しく実践することが重要です。特に、ストレスや精神疾患を抱える方に向けたプライベートマインドフルネスでは、次のポイントが求められます。
指導者としての役割と重要性
- 個々の状態を見極め、適切な指導を行う
- クライアントの精神状態やストレスレベルを把握し、負担をかけすぎないよう調整する。
- 一般的な瞑想指導とは異なり、心理的なケアを含めた対応が求められる。
- 正しいマインドフルネスの理解を伝える
- 「何もしない」「リラックスする」だけではなく、意識的に「今」に向き合う訓練であることを説明。
- 誤った実践(過度な集中による焦りや、自責感の強化)を防ぐ。
- クライアントに応じたアプローチを提供する
- 一人ひとりの特性に合わせ、最適なプログラムを構築。
- 必要に応じて、呼吸法・ボディスキャン・歩行瞑想・慈悲の瞑想など、異なる手法を組み合わせる。
- 長期的な実践につなげるサポート
- セッション後も日常で実践できるよう、具体的な方法を指導。
- 定期的なフォローアップを行い、マインドフルネスを生活に定着させる。
こうしたポイントを押さえながら、一対一のプライベートな環境でクライアントに深く寄り添うことで、より効果的なサポートが可能になります。
クリック ⇒

